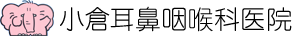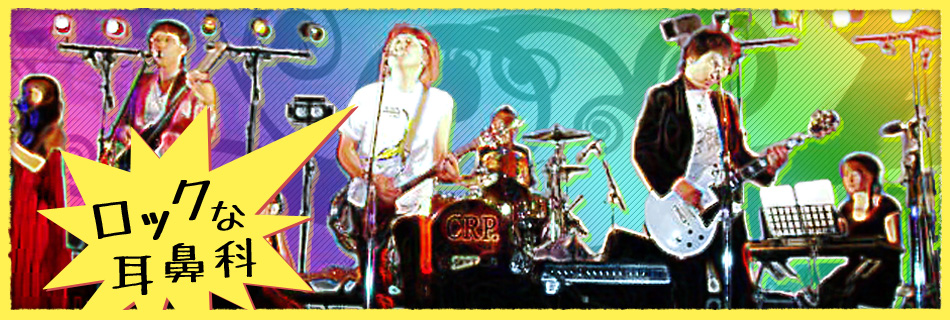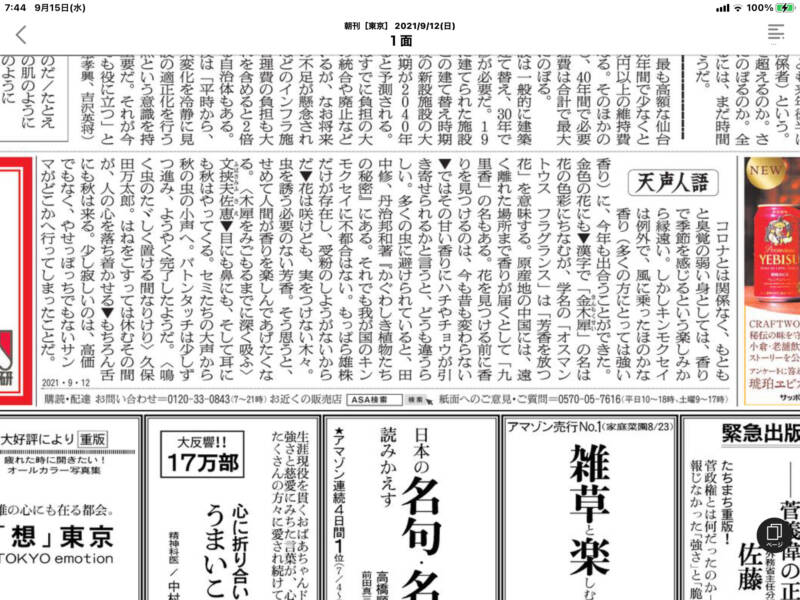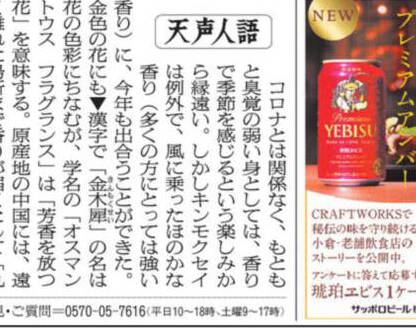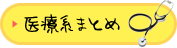2024.04.01
「四月一日」と書いて「わたぬき」と読む名字があることは結構有名である。
四月になると暖かくなるので、
着物から綿を抜いたりしていたので、
これに由来する「考え落ち」的な読み方である。
同じように「小鳥遊」という名字があって、
これは「たかなし」と読むそうだ。
鷹がいないと、小鳥が安心して遊べるから
鷹無しで、小鳥遊というこれもひねった読み方です。
この間「白」さんという方が来院されました。
「しろ」さん、「はく」さんではありません。
「百」という文字には「もも」という読みがあります。
山口百恵ちゃんの「もも」です。
なので百から一を引いた「九十九」を
あと一つで「次ぐもも」から
「つくも」と読みます。
なので「百」から一を引いた「白」で、
このかたは「つくもさん」でした。
多くの名字は明治維新以降にできたものだと思われますが、
「わたぬき」さん「たかなし」さん「つくも」さんなどのご先祖は
さぞかし頭がよく、洒落がきいてて、
ちょっとひねくれものだったんでしょうね。


2023.12.05
外来患者さんが、
「ノドの具合が悪く、咳き込み過ぎて嗚咽しちゃいます。」
と訴える。
あー、嗚咽ねー。
患者さんが言いたいのは、
咳き込んで吐きそうになってしまう、
ということだと思われますが、
これを「嗚咽しそうになる」というのは誤用です。
「嗚咽」とは声を詰まらせて泣くこと、むせび泣くこと、で
「変わり果てた彼の遺体を見て嗚咽した」
「葬儀会場では故人との別れを悼んだ友人がこらえきれず嗚咽を漏らしていた」
などと用います。
それが、近年、若い人の間で誤用されているようです。
何で、全然違う意味なのに、と思いますが、
ひょっとしたら「嗚咽」の「おえつ」という語音が、
「おえっとなる」に似てるから?
まさかと思う、ちょっと信じがたい話ですが、
どうもそうみたいです。
では、正しくはなんというかというと、
「えずく」で漢字で書くと「嘔吐く」でしょうね。
ただしPCなどでは、この変換は出来ないようなので、
特殊な表現なのかも。
そんなわけで、聴いてるこっちが恥ずかしくなるので
「嗚咽」の誤用には注意してください。
とっさに「えずく」が出なければ、
「吐きそうになる」「ゲロが出そうになる」でよろしい。
今回はその場では聞き流しましたが、
教えてあげたほうが良かったのかなあ。


2023.11.08
仕事柄、医学、生物学はむろん専門分野であるが、
物理学、化学、歴史、地理、数学、語学、文学などと比べて、
ダントツで苦手なのが経済学。
そもそも全く興味がないので、
苦手以前に学ぼうという気もない。
幸い、わが国では医者は金儲けのことなど考えずに、
まじめに患者さんのために診療をしてれば
きちんと暮らしていけることになっているが、
株式や投資、経営や仕入れ、営業、資産運用知識などもまったくゼロなので、
ワタシが医者以外の自営業をやっていたら、
間違いなく倒産してるだろう。
先日床屋さんに行ったとき、
「先生のとこ、インボイス制度になってどうですか?」
と訊ねられた。
うわー、キター。💦
インボイス制度、なんかテレビのニュースで耳にしたことはあるけれど
何のことだか、全く知らない。
ダウ平均株価のダウがいまだに意味不明なのに、
インボイスなんてわかるわけない。
そもそもインボイスなんて英単語、習った覚えがない。
ワタシの心の中の本音の答えは
「インボイス制度って、何?」
であったが、
立場上、そんなことを言うと非常にマズイ感じがした。
ここは、なんとか、話を合わせなければ。
「ああ、インボイスね・・・・」
などといいながら、心の中で
「インボイス、インボイス、ああ、何のことだったけ・・・」
と、必死に記憶の断片をたどる。
と、床屋さんが
「私のところなんか、領収書なんか出さないんで関係ないんですけど、
アピタなんかだと消費税の数字が変わっちゃう、って
騒いでましたよ。」
ああ、インボイスは消費税関連のナンタラか。
そこで、おもむろに
「病院は消費税もらわないんで、関係ないんですよ。」
と、答えてみた。
あー、そうなんですか、なるほど。
と言われて、何とかその場は丸く収まった。
あー、危ないところだった。
だが、なんとか、無事、切り抜けたぞ。
ところで、本当に関係なしで、良いんですよね?


2023.06.20
夏風邪の季節になってきました。
以前も書きましたが、夏風邪は「夏にひく風邪」ではなく、
夏の高温多湿な環境で元気になる
コクサッキーウイルスなどのエンテロウイルス族やアデノウイルス
による風邪です。
すなわち「ヘルパンギーナ」「手足口病」「咽頭結膜熱(プール熱)」
の3つを「夏風邪」と呼びます。
なので、「内科で夏風邪と言われました。」
という患者さんには
どの夏風邪でしたか、と質問するのですが、
大概は答えられません。
患者さんが聞き漏らしたのか、
また勝手に夏風邪と思い込んだのか、
はたまた夏風邪を知らない内科医が、
テキトーなことを言ったのか・・・・。
RSウイルスや、コロナウイルス、ライノウイルスは、
夏にひいても夏風邪とは言いません。
冬風邪という言葉はありませんがいわば冬風邪です。
さて、今は雨のシーズンですが、
気象用語では
強い雨、激しい雨、非常に強い雨、猛烈な雨という言葉は、
それぞれ1時間雨量が20mm以上30mm未満、
30mm以上50mm未満、50mm以上80mm未満、
80mm以上と決められています。
なので、もし気象予報士の知り合いがいた場合、
「昨日は猛烈な雨だったねえ。」
と言った場合、
「いやあ、昨日のは猛烈な雨では無く、
非常に激しい雨だったんじゃない?」
というような会話になるのでしょうか。


2023.01.24
天気予報やニュースなどでは、
10年に一度の強烈な寒気が流れ込むとの話題が
繰り返し報道されています。
今朝の朝日新聞の天声人語でも、
「八甲田山死の彷徨」を引用しながら寒さへの注意を
喚起していましたが
その中の
「かつて経験したことのない寒気だった」
というくだりを
「かつて経験したことのないサムケだった」
と読んでしまい、一瞬、えぅ?と思ってしまった。
仕事がらカルテの記載などでも
「寒気」は「カンキ」ではなく、
「サムケ」と読むことの方が圧倒的に多いので。
気象庁の人は、まず「カンキ」と読むのであろう。
高校生は「生物」を「セイブツ」と読むが、
食料品を扱ってる人は「ナマモノ」と読むだろうし、
一般には「食べてる最中だ」は「食べてるサイチュウだ」でも、
和菓子屋さんは「食べてるモナカだ」としか読まないだろうなあ。
あ、ワタシの苗字、九州地方では「コクラ」らしいです。


2022.07.27
サル痘に関するNHKのニュースで、
アナウンサーの女性が「発疹」を「ハッシン」と発音していました。
えっ、これって「ホッシン」じゃねえの、と違和感があり。
調べてみると、意外な事実が判明。
「発疹」の読みは「ホッシン」も「ハッシン」も正解。
だが、どとらかというと「ハッシン」の方が正しく、
NHKは「ハッシン」に統一してるらしい。
なんて、こった。
逆だと思っていた。
さらに調べると「ホッシン」は
特に医療現場で、そう発音されることが多いという。
ナルホド。
医療現場特有の発音はあります。
たとえば「腔」の字には正しくは「コウ」という読みしかありませんが、
医療現場では「胸腔」「鼻腔」「口腔」など、
すべて「クウ」と発音します。
これはおそらく聞き間違いを防ぐためだと思われ、
「ビコウ」というと「鼻孔」で鼻の穴のことになります。
手術後の「抜糸」は、歯科では「抜歯」と区別するために、
「バツイト」というと聞いたことがあります。
他にも医療現場では「発赤(ほっせき)」「発作(ほっさ)」など
「発」を「ホッ」の発音で呼ぶことが多いですが、
さすがに「発作」を「ハッサ」とは呼ぶことはないものの
「発赤」に対しては国語辞典では「ハッセキ」の読みもあるようです。
それにしても「早急」はもともと「サッキュウ」だが、
「ソウキュウ」と誤読する人が増えたので、
最近は「ソウキュウ」も正しいことになったのと同じく
「ハッシン」も誤読の一般化だと思ってて
「ハッシン」と発音するヒトを
今まで心ひそかにバカにしていたが、オレの方がバカだったとは。
ソウキュウに考えを改めなければ。


2022.05.22
先日来院されたおばあちゃん。
「なんか、ミミズが鳴いてる、と思ってたんだけど、
ずっと消えないので耳鳴りだった。」
そういえば、春になって暖かくなると、
夕暮れどきに何処からともなくジーっという音が聞こえます。
これを「ミミズの鳴き声」と称することがあり、
俳句でも「蚯蚓鳴く」という言い回しがあります。
しかし、ミミズは鳴きません。
発声器官もセミやコオロギのような音を発生する機構もないので
地面から聞こえる「ジー」っという音は
実際にはケラの鳴き声と言われています。
だが「蚯蚓鳴く」は秋の季語だそうで、
春の季語では「亀鳴くや」となるそうです。
いや、カメも鳴かないぞ。
我々が春の宵に耳にする「ジー」という音は、
「クビキリギリス」という
バッタの仲間の声だと思います。
いかにも耳鳴りっぽい無機質な音で、
同じバッタ目でもスズムシやコオロギのような風情はありませんね。
秋に成虫になり冬眠して冬を越すので、
他の虫より早く春から鳴きだすらしいです。
耳鳴りの音を「セミの鳴き声のよう」
と表現される患者さんは非常に多いですが、
「クビキリギリスのような耳鳴りがします、」
と言って来院された患者さんには
耳鼻科医になって40年近くたちますが
いまだに一人も逢ったことがありません。


2022.03.03
先日のNHKのあさイチ。
特集は「魅力がありすぎる徳島」。

「美しすぎる」

「すごすぎる」

「野性味あふれすぎる」

いつ頃からでしょうが、
若者言葉として「〜過ぎる」という言葉を
「とても〜である」という意味、
あるいはその強調形として用いる例が
目につくようになりました。
いわく「このスイーツ、美味し過ぎ❤️」
「槙野のあのシュートは凄過ぎですね。」
「双子のパンダ、可愛過ぎます。」
これらはいずれも「とても〜である」を
さらに強調しようとして用いてる、
ちょっと前なら「チョー〜」で
表現された言い回しです。
「このスイーツ、チョー美味しい❤️」
「槙野のあのヘッド、チョー凄かった。」
「双子のパンダ、チョー可愛いです。」
「〜過ぎる」という言葉はもともと形容詞を伴って
「あまりに〜なので(かえって)・・・ではない」
という否定の文脈で用いられて来ました。
英語でいえば「too〜to …」構文というやつで
「He is too old to drive a car.」
「彼は車の運転をするには歳を取り過ぎている。」
とか
「The ice on the lake is too thin to skate on.」
「この湖の氷は薄過ぎてスケートは出来ないなあ。」
という類です。
それがいつの間にか最上級の言い方に変わったのは、
「美人すぎる海女さん」なんてのが
ニュースになった10年くらい前あたりからでしょうか。
だが、この時点では
「あまりに美人すぎるので本物の海女さんではなく、
(やらせで)モデルさんが演じているんじゃないかと思っちゃうほど」
という従来の文法になっていたのですが、
この前半部分が切り取られた形で拡散しました。
さらに最近の言い回しと合体して
「神過ぎる対応」とか
「このゲーム、ツボ過ぎる」
「天使過ぎるアイドル」
なんていう表現は、
10年前だったらなんのこと言ってるのか
まったく理解できなかったと思う。
古くは1971年の野口五郎の大ヒット曲に
「君が美し過ぎて」というのがあります。
千家和也作詞のこの歌詞だと
「美し過ぎて、君が怖い」となっています。
歌詞の内容は
「君はとても美しいのでボクは魅力を感じているが
あまりに美し過ぎると怖いという
(反対の)感情が湧いてくることがある、
それによってボクは苦しめられ、
間違いを起こしそうだ、と歌っているので
昨今の「〜過ぎて」とは違い、
従来の用法を踏襲しているといえます。
言葉はうつろいゆくものとはいえ、
オジサンには、どうも最近の「〜過ぎて」という
この表現は抵抗があります。
若者には抵抗ないのかしら。
例えば、ある会社の会議で
若手社員「部長、ワタシが考えたこの企画、どうでしょうか。」
年輩部長「うーむ、こりゃあ、キミ、斬新過ぎるね。」
若手社員「良かったー、ありがとうございます。」
なんていう、行き違いは無いのだろうか。
新型コロナオミクロン株に罹った患者さんの
インタビューをNHKの朝のニュースで流していました。
「熱が高過ぎて寝られませんでした。」
この人の場合「熱が高すぎて寝られなかった。」
というコメントは
「熱が多少あっても寝られるが、
高さがその限度を越していたので寝られなかった。」
ということなので、従来の表現を逸脱してはいないのですが、
本来なら「熱がとても高くて寝られなかった‘。」
という表現だろうかと思われます。
しかし、これも段々定着しちゃうのかも。
いや、NHKのあさイチでやってるのだから、
もう正しい用法なのか。


2021.11.20
外来にかかった子供を見てスタッフが
「あれ、○○ちゃん、前髪アシメになってるね。」
と言いました。
「アシメ」という言葉は初めて聞きましたが、
瞬間的に「アシンメトリー(左右非対称)」
のことだろうと思いましたが、
やはりその通りだったようです。
「a」は否定を示す接頭辞ですが、
医学用語では比較的よく用いられます。
肺、呼吸を表す「pnea」という言葉に「a」がつくと
「apnea」=無呼吸になります。
音、声を表す、iPhone、テレフォンの「phone」とくっついて
「aphonia」は「失声(症)」という意味になります。
鼻は「nose」ですが、これにくっついて「anosmia」になると
「嗅覚脱失」「無臭症」ということになります。
~血症という意味の「nemia」に「a」がついた
「anemia」は「貧血」です。
さらに「aplastic anemia」というのがあって、
これは「作る」という意味の「plastic」、
プラスチックの語源ですが、
これに「a」がくっついて否定されていますので、
「再生不良性貧血」という病気のことです。
ちなみに医療関係者はしばしばこの病気のことを
ギョーカイ用語で「アプラ」と呼びます。
だから「アシメ」がすぐわかったのかも。


2021.09.15
先日の朝日新聞の天声人語に
「金木犀」の話題がありました。
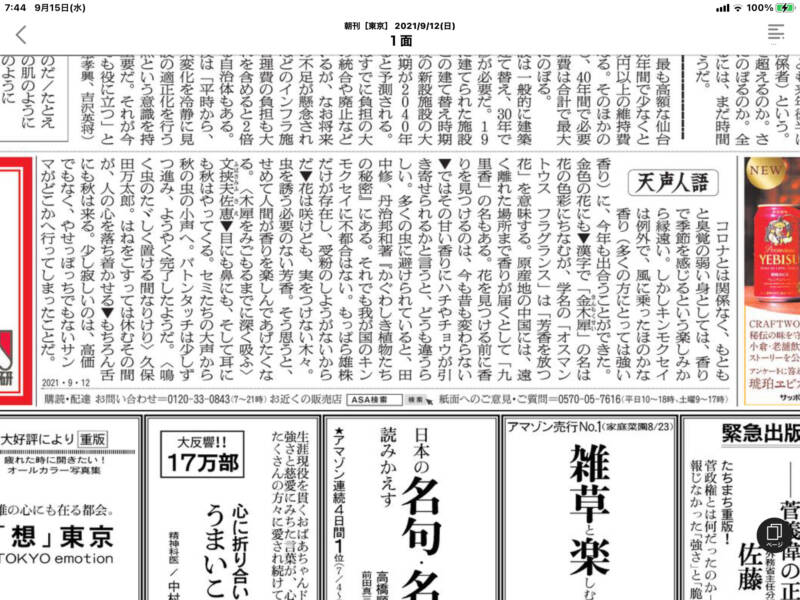
季節の話題として毎年この時期取り上げられる「金木犀」ですが
気になったのは2行目にある「臭覚の弱い身」のくだり。
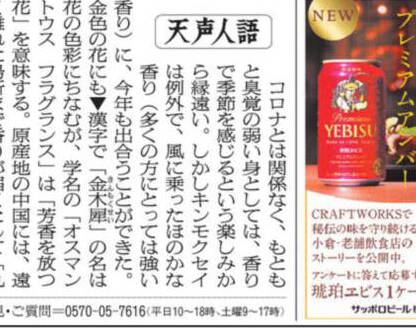
天下の朝日新聞ともあろうものが、
これは「嗅覚」の間違いではないか。
「臭(シュウ)」は「臭う」、
「嗅(キュウ)」は「嗅ぐ」であり、
ニオイを感じとる感覚は「嗅覚(キュウカク)」といいます。
ワタシは毎年看護学校の講義の1時間目に
耳鼻咽喉科は「感覚器」を扱い、
「視覚」「聴覚」「嗅覚」「味覚」「触覚」の五感のうち3つを担当し、
しかももう一つの感覚である「平衡(感)覚」も
耳鼻咽喉科の領域なのですよ、と説明します。
そのときに、
ときどき「臭覚」という人がいますが
正しくは「嗅覚」なので、
プロとなるあなたたちは、そういう恥ずかしい間違いをしないように、
と付け加えます。
ところが、今回ちょっとネットで調べてみると
なんと辞書では「臭覚(しゅうかく);嗅覚に同じ」となっていて
必ずしも誤用とは言えないないらしい。
ちょと前まではこんなことは無かったはず。
これは、おそらく誤用が多用されて一般化した例でしょう。
言葉というモノはまさに生き物なので、
時代に応じて変化していくのが習わしです。
古文で習うような言葉と現代語ではだいぶ言い回しが違い、
それは長い期間に変化してきたものですが、
変化の中にはたとえ当初は誤用であっても
その言葉が多く「流通」すれば
それがやがて誤用ではなくなる、というケースがあります。
しかもそういうことはかなり短時間で起こり、
ワタシの60年余りの人生の時間の中でも
変化を目にすることができます。
例えば「重複」や「早急」という言葉です。
「重複」は中学生のころ「ちょうふく」と読むと教わりましたが、
「じゅうふく」と誤読する人が多くなった結果、
今はどちらでも可、になっています。
「早急」は「さっきゅう」がもともとの読み方ですが、
「そうきゅう」でもいいことになり、
今や「そうきゅう」の方が多数派かも。
せっかく覚えた「正しい読み方」が、
誤読者の「数の理論」でなし崩しになるのはちょっとクヤシイ。
「重複」という単語は国語の教科書で、
スポーツ中継のアナウンサーの表現か何かの文章で、
「重複した表現はかえって迫力をそぐ」
という文章で出てきたことまで覚えています。
この字の「読み」は
期末だか、中間だかの試験のヤマの一つだったような・・・・。
でも、できれば正しく「嗅覚」という言葉を使いたいものです。
国民の大多数が麻生財務大臣並みの国語力だったら
「未曾有」の読みも「みぞゆう」になるかも知れんなあ。