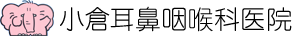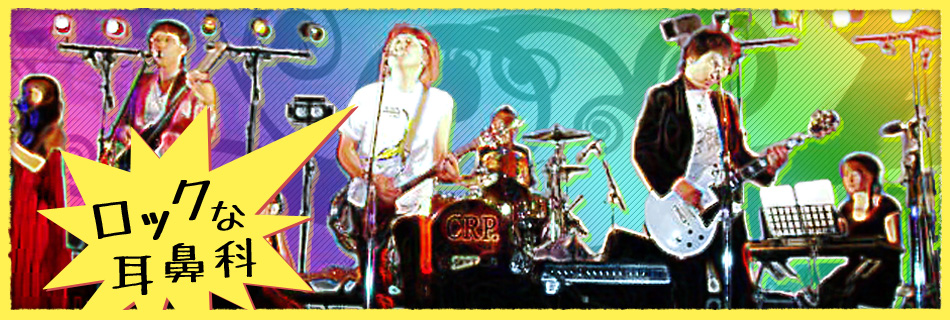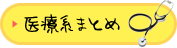2023.11.19
続きです。
朝だ。

このホテル、開業したばかりで、
従業員の「こなれて無い感」が目にはついたが、
朝食も美味しく、なかなかいいホテルでした。

ただ立地の関係で、棟が2つに分かれていて、
ちょっと分かりにくい。
レストランに行くのに迷子になってしまった。

さて昨日は、夜、寒かったので
タクシーでホテルまで来ましたが、
今朝は天気もいいので歩いて会場まで。

おー、アンパンマンミュージアム、ここか。
ウチの子はアンパンマンにはあまり興味なかったなあ。

約20分で会場に着きました。
今日もきちんと朝イチからの参加です。

単位を取得する共通講習、領域講習の際には
入室前に入り口のPCのカードリーダーにタッチ。

そして退室時にもタッチをして登録をしなくてはいけないのだが、
どうも導線の設定が悪く、渋滞します。
同じ会場であれば何とかなるが、
他会場に移動する際、若干遅刻したりします。

さて、本日も午後4時過ぎまで講習がありますが、
訳あって、半日で会場を後にします。

実は、夕方までに前橋まで行かねばならない用事があり。

ランチョンセミナーのお弁当もいただかずに、お昼は列車内で駅弁。

崎陽軒ファンのワタシですが、
今回は定番の「シウマイ弁当」ではなく
「横濱炒飯弁当」で。
これもダイスキ。

さて、夕方帰宅し、今度はクルマで前橋に向かう。
ホントに、オレ、忙しい。



2023.11.18
そんなわけで11月18日~19日は、
第37回日本耳鼻咽喉科学会秋季大会。

秋季大会というと、品川に前泊して始発の新幹線に乗ったり
前日最終の新幹線で深夜に現地入りしたりでしたが、
今回は始発のりょうもう号でOK。
といっても5時起きです。

5時52分発の特急りょうもう号。
なんと車内で日赤のS先生とご一緒でした。
まあ、学会を最初から、となればこの列車です。

久喜駅で上野東京ラインに乗り換えれば横浜まで直通。

グリーン車があるのでラクです。

乗り換え時に久喜駅で買ったパンで朝食。

黒豚コロッケバンズ、美味しかった。

この電車は熱海行き。このまま
あー、このまま熱海まで行っちゃいたいなあ。

横浜駅でみなとみらい線に乗り換え。

あー、そろそろ巷はもうクリスマスか。

8時半前に会場に着きました。

これから夜までみっちり講義です。

パシフィコ横浜の国際会議場。

ここは椅子の袖からテーブルが出るので
ノートを取りやすい。

それにしても新専門医制度が導入されてから、
この日耳鼻秋季大会(旧称耳鼻咽喉科専門医講習会)
午後6時40分まで8コマ。
10分間の休み時間は、退出して単位記録して再入場、
あるいは他会場への移動なので、
ボーッとしてる時間はない。

それでもやらねばならんのだ。

お昼もお弁当を食べながら講義を受ける。
ムカシはこのような制度はなかった。
まあ、昼メシの場所を探しに行かなくてもよくなったわけだが。
以前、神戸の専門医講習会で昼食難民になったことがあった。

お弁当。
和風と中華風から選べる。
これは中華風。
ホントは横浜中華街でランチ食べたい。

午後に1時間空白があり、ここは機器展示に行って
業者の説明を聞いてこい、
というものでスタンプもらうと景品がもらえる。

景品なんかどうでもいいから休んでようと思ったが、
妻がどうしても欲しい景品があるので、
説明聴いてスタンプもらおうという。

シマエナガボールペンとマスキングテープのセット。
これであったか。
ワタシのスタンプも献上しました。

さて、その後も共通講習、領域講習を履修し、
最後の学術セミナーは頭頚部がんの免疫療法の話で
開業医にとっては直接関係ないのでパスさせてもらい
ホテルに向かいます。
朝から1コマ1時間の講義を7コマ、
みっちり7時間も聴けば、もういいでしょう。
今回泊まったのはヒルトン横浜。

今年9月23日に開業したばかりの新しいホテル。
予約うっかりしてたので、会場近くのホテルはいっぱいだったが、
ここは新しいせいか空いていた。

ホテル近くに人の群れ。
実はここはKアリーナというホールが隣接しており、
調べたら今夜は「ゆず」のコンサートであった。

このKアリーナもこの9月29日に開業したばかり。
このあたり元は何だったのか、と調べると、
2016年まで横浜Fマリノスのトレーニング施設があったらしい。

さて、夕食は講習会のあとは疲れて外に出るのも大変だろうと考え、
ホテル内のレストランを予約しておきました。

ホテルのレストランとしてはわりとカジュアルな雰囲気で、
お料理もたいへん美味しかったです。








さあ、また明日。

続く。


2023.11.14
またまたの学会休診で恐縮なのですが、
日本耳鼻咽喉科学会秋季大会参加のため、
11月18日土曜日は休診です。

秋季大会は毎年5月に行われる日本耳鼻咽喉科学会総会と並んで、
耳鼻咽喉科医にとって最も重要な学会です。
5月の総会が、映画監督や業界著名人の特別講演や、
ミニコンサートやお笑いライブなどもある「お祭り」的な要素があるのに対し、
かつて「専門医講習会」という名目だったこの秋季大会は、
がっちり勉強させられる「ガチ」な学会です。
日本全国を北海道・東北、関東・甲信越、
中部・東海、近畿・和歌山、中国・四国、九州・沖縄の
6つのブロックに分けた持ち回り開催で、
以前は担当エリアで開催されていました。
ところが専門医制度が変わって、参加人数が激増したため、
地方での開催が困難になって、
主として首都圏、関西圏での交互開催になってきました。
今回もポスターを見てわかるように、
北海道・東北ブロックの主催ですが、
会場は横浜です。

せめて、地方なら観光できなきくても
往復でちょっとした旅行気分も味わえるのだが。
ポスターにあしらわれた北海道のお花畑、岩木山、なまはげ、中尊寺、
銀山温泉、伊達政宗公、赤べこなどが恨めしい。
まあ、横浜ならば、朝自宅を出れば間に合うわけなので、
いつも地方開催でしているような、
開始時間に間に合うように、
東京に前泊して、新幹線の始発に乗ったり、
前日深夜に会場近くのホテルにたどり着いたり、
といった苦労はしなくて済むのですが。
そんなわけで、11月18日土曜日は休診になりますので、
ご了承ください。
たぶん、全国的に耳鼻咽喉科医院はかなりの割合で休診でしょう。
学会シーズンは春から秋なので、
この後、来年5月の総会まで学会休診はありません。


2023.11.12
続きです。
今日は雨。
3日間の天候は晴れ→曇り→雨ということになった。
出発・観光→学会・とり天→学会・帰宅という点で天候に恵まれた。

朝食前に露天風呂に入り、ちょっと温泉気分を味わって。

さああと半日。

駅のコインロッカーに荷物を預け、
タクシーで会場へ。

あさイチで会場入り。

昨日駅前ではできなかったが、
周りに人がいなかったので、ここでは顔出ししてみました。
何のキャラクターなのかは、不明。

さて今日は午前中3コマ聴講して、
帰路につく予定ですが後ろの2コマが、
単位取得関連講演なので、
最後の講演は、途中退室してしまうと単位が取得できず。
しかし、帰りの飛行機の時間から逆算すると、
大分空港発が13時40分、
それに間に合うバス便エアライナーが
別府駅11時42分発。
ローカル空港は飛行機の便数が少ないので、
おのずと決まってしまう。

さらにそれに間に合わせるためには
ビーコンプラザ前バス停を11時14分に出る
路線バスに乗らなければならない。
タクシーはなかなかつかまらないのでリスクが大きい。
最後のパネルディスカッションが11時10分まであるので
相当タイトなスケジュール。
最後のパネルディスカッションは
5人の演者のうち一人がキャンセルしたので
演者4人になり短くなるかと一瞬期待したのだが、
やっぱり、ディスカッションの時間が長くなっただけであった。
パネルディスカッション終了の司会者の言葉が終わらないうちに
会場を飛び出し、出口でパソコンに会員カードをタッチして、
無事単位を取得したあと、
脱兎のごとく、会場を飛び出す。
バス停は、あの道を渡った向こう側。
距離的には、近い。

何とか、間に合った。


無事、バスに乗車。
今回の旅はこんなシチュエーションが多い。

駅に着き、コインロッカーから荷物を出し、
空港バスの列に並ぶ。
空港まで約1時間。
チケットは買ってあるが、座席指定ではないので、
補助席や、立ち乗りではなく、
ちゃんとしたシートに座りたい。

バスは大型バスで、混んではいたが満席ではなかった。

これでホッとしました。

楽しかった別府の学会もこれでおしまい。

本当は水族館や高崎山のサル公園も行きたかったが、
あくまで学会旅行なので仕方がない。

それにしても観光の1日目がいい天気でよかった。

大分空港。

搭乗。

楽しみはプレミアムクラスのお昼ごはん。

プレミアムクラスはちょっとお高いが、
60歳を過ぎればこの程度の贅沢は許される?

特急列車から食堂車が無くなった今、
この機内食はまた旅気分を味わう食事として貴重。
しかも、移動中に食べられるので時間の無駄がない。
大分→東京の1時間ちょっとのフライトではちょっとあわただしいが。

いつもビールのワタシですが、
今回は白ワインをいただきました。

羽田から、モノレール、京浜東北線、日比谷線を乗り継ぎ、

特急りょうもう号へ。
車内ではスマホでDAZNの見逃し配信を観ながら帰ってきました。
その結果は後ほど。

2泊3日の温泉付き学会旅行、充実してました。
学会で得た最新の知見も、折を見てブログにします。


2023.11.11
続きです。
さて、今日からは学会です。
昨日はよい天気でしたが、今日は曇り。

あさイチに間に合うように学会場へ。

ここは別府国際コンベンションセンターですが、
通称「ビーコンプラザ」というそうです。

別府のBとコンベンションで「ビーコン」らしいが、
医者にとっては「ビーコン」とは医学生時代の再試験の意味なので、
このネーミングはちょっと引っかかる。
それにしても人影がない。

事前登録がしてあったので参加受付をして
ネームカードをもらいます。
このあと、午前中3コマ。

この小児耳鼻咽喉科学会は
第9回アジア小児耳鼻咽喉科学会(Asia Pediatric Otolaryngology:APOG)との
共同開催となっていたので、
講演の半分近くは英語によるもの。
英語力がないので
日本人の英語はまだわかるが、
シンガポールや中国の人の英語は聴き取りにくい。
スライドが頼りです。

3コマ聴講し、単位も取得。
お昼ご飯に関してはプランがあったので、
4コマ目のお昼からのランチョンセミナーは無料で配られるお弁当は辞退して、
聴講だけしました。

そして、その後タクシーを呼んで向かったのが、
ここ東洋軒は大分名物「とり天」の発祥のお店。

しかし、それだけに超人気店で
平日の午後だというのに60分待ち。
シートに名前を書いてほどなくこのボードは
80分待ちになっていた。

まあ、店内で本など読みながらのんびり待ちます。
タレント、有名人のサインがいっぱいです。

外にも多くの人が待っていました。

実は東洋軒は別府駅東にも支店があり、
駅に近いそっちでもいいかなと思ってたのですが、
なんと前日のニュースでこんなことになっちょりました。
なので、わざわざ遠いこちらの本店に来たわけですが、

さらに、翌日、つまり今日のスマホの画面では

つまり本日営業してるのはこの店舗のみ。
うーむ、これは、長く待つのも仕方がない。
結局、席に着くまでに74分49秒かかった。

さて東洋軒は大正15年に創業。
ということは間もなく創業100年になる老舗。
しかもワレワレが宿泊している亀の井ホテルの初代司厨長であったか。

その割には飾らないカジュアルな食堂であった。
むろん注文するのは本家とり天定食。

ただし柚子とり天も気になるので、
別々にとってシェアすることにしました。

これが本家柚子とり天定食。

こっちが本家とり天定食。

シェアしていただきました。

まあ、味はとり天なので美味しいに決まってる。
そこそこ予想のつく味です。
背後に立っているのは中京テレビの人で、
カメラ取材をしていました。
オモウマい店という番組だそうです。

なんだかアバウトなカメラアングルですが、
どんな番組になるのでしょうか。

美味しかったのと、有名店を制覇したので大満足。
しかし、料理がくるまでにもだいぶかかったので
とり天も食ったが、
だいぶ時間も食ってしまった。
すっかり日が傾いて夕方になってしまいました。

しかも、タクシーが呼んでもなかなか来ない。
ようやくタクシーが来たが、
夕方の単位講習に間に合わないかもなので、
ここで行く先を変更。

せっかくなのでロープウェーに乗ってみます。(^^;)

100人乗りのゴンドラ、鶴見岳山頂まで10分。

平日夕方ですが、結構混んでました。

もう、日が暮れてしまう。

山頂は標高1300メートル。
紅葉はすでに終わりかけ。

そして、寒い。

だが見事な眺めでした。
山の形が別府の町に影になっています。

帰りは路線バスで帰るため、山頂に4時10分に着き、
4時20分の下りロープウェーに乗ります。

忙しいスケジュールですが、
この16時34分のバスを逃すと、次は1時間近くあとなので。
このバスアプリ、便利でした。

バスが来ました。
Suicaが使えるので助かります。
これで別府駅まで。

別府駅で土産物を買いました。
ここに顔出す勇気がなかった。

温泉に入った後、
今夜の夕食はホテルの1階にある
郷土料理のお店で。

例の地獄めぐりの発案者、この亀の井ホテルの創業者の
油屋熊八氏にちなんだお店です。

このヒト、いわば別府を有名観光地にした功労者で
駅前には銅像がありました。
万歳してる銅像も珍しい。

このキャッチコピーもなかなか。
海は瀬戸内なのか。

エビスビールでは常にえびす顔。

地元の関アジ、関サバもいただきましたが、

大分の郷土料理、だんご汁、初体験。

実は「だんご汁」といっても、入っているのは「だんご」ではない。
丸く見えるのはサトイモで、これは関係ありません。

この太いうどん状のものを「だんご」と称するらしい。
山梨の「ほうとう」群馬の「おきりこみ」に近いものだ。
詳しい解説はこちら。
おこりこみとほうとうの違いはこちらにありました。

おや、いつの間にか、また抹茶アイスを食べている。

そして、大分といえば「西の関」。
九州を代表する銘酒です。

油屋熊八の偉業に敬意を払いつつ。

明日、最終日。


2023.11.10
続きです。
別府到着が13時26分。
明日からが学会なので観光できるのはこの午後のみ。
インターネットから別府名物地獄めぐりの
定期観光バスをあらかじめ予約しておいた。
ところが、ワタシが予約確認メールをどこかに失くしてしまったので
予約の確認に手間取ってしまった。
なんとか無事確認がとれ、乗車券をゲット。

午後2時出発のバスを待つ。

やって来たのは鬼のツノをはやしたバスであった。

平日だが、けっこうお客さんはいます。

実は地獄めぐりは2回目。
今をさかのぼること30数年前、
また小さかった長男を博多のおじいちゃんの家に預けて、
妻と2人で来たことがあり。

その時も同じ観光バスに乗ったのだが
記憶は断片的。

バスを降り、最初の目的地、海地獄へ。

別府地獄めぐりは昭和3年に
亀の井ホテルの創業者、油屋熊八がはじめた
地獄めぐり遊覧バスが始まり。
ちなみにこの時、彼の考案で
全国で初めて女性バスガイドなるものが登場した。
このお姉さんは、由緒あるその末裔ということになります。

しかし、その場で初めて同乗する30人以上のお客さんを
たった1人でもれなくバスで連れまわして誘導する、
というのは大変な業務だ。

天気も良く、ちょっと紅葉もいい感じ。

海地獄手前の蓮の池には、熱帯のスイレン、

そしてオオオニバスが。

海地獄は硫酸鉄の含有によりコバルトブルーに見えるそうです。

ガイドさんに撮ってもらいました。

湯気で海地獄の「海面」が見えません。

温室にはオオオニバス。

スイレンもきれいです。
地獄というよりは蓮の花が咲く極楽浄土だ。

海地獄から歩いて鬼石坊主地獄。

泥の中から湧き出る温泉が坊主の頭に見えることから命名。
坊主というよりなんとなく「妖怪人間ベム」のオープニングを思い出させる。
(動画56秒ころから)

実は、坊主地獄という施設は別にあって、
ここは鬼石地獄と新坊主地獄を合わせて「鬼石坊主地獄」として園地を整備したもの。
閉鎖されていたが2002年(平成14年)12月16日に約 40年ぶりにリニューアルオープン。
ということは前回来たときは無かった?

「別府地獄組合」というものがあって、これに加盟している7施設が
地獄めぐりの対象で、「坊主地獄」はこれに加盟していないらしい。
この辺、宇都宮餃子会に加盟していない「正嗣」みたいなものか?

続いて、徒歩でかまど地獄、鬼山地獄、白池地獄方面へ。

途中、あちこちから蒸気が噴き出ています。

まずはかまど地獄。

6つの地獄があり、
それぞれ「地獄の一丁目」から「六丁目」と名付けられている。

いろいろな色の変わった温泉が見られる、ということです。

この鬼がシンボル。

2丁目、3丁目


4丁目。
蒸気の実演実験をやっていました。


5丁目はエメラルドグリーン。

そして6丁目。
こちらは赤い。

隣同士なのに色が違う。

さて、かまど地獄を終え、

すぐ近く、鬼山地獄です。

ここにも鬼が。

ここの目玉はワニです。

温泉の熱を利用して、ワニを多く飼育しています。
鬼山地獄というよりワニ山地獄だな。

007にこんなシーンがあったなあ。

5つ目の地獄は白池地獄。

白い池。
地獄のイメージではないなあ。

ここには、別府温泉を開いたといわれる一遍上人の像があります。

そして、熱帯魚館があります。
なんか昭和レトロの良い感じ。

観光客を集めるために、ワニや熱帯魚など、
あれこれ工夫してるわけです。

さてここから、またバスに乗ってあと2か所。

車窓から見えるこの風景が
残したい日本の原風景10選のランキング2位に選ばれたそうです。

最後2つは龍巻地獄と血の池地獄。
龍巻地獄は間欠泉で入り口の赤いランプがともると、
噴出時間が近いということだそうです。
今、点灯しました。

なので、さっそく入場して待つことしばし。

来ました。

本来は30メートルくらい上がるらしいですが、
観光客の安全を確保するために
このような石の覆いをつけたそうです。

せっかくなら高く吹き上がったところを見てみたいもんだ。

ちょっともったいない。
写真で撮ると下から吹き上がってるんだか、
上から流れ落ちてるんだかよくわかりませんね。

そして、最後は血の池地獄。

なるほど、青い海地獄や白池地獄は地獄、という感じではないが
これは地獄っぽい。

赤い色は酸化鉄によるという。

何にでも効くという血の池軟膏が売られていました。

熱血、なるほど、たしかに。

おお、血の池地獄はサガン鳥栖のオフィシャルスポンサーなのか。
大分トリニータではないのね。
選手はケガをすると血の池軟膏、使ってるのだろうか。

さて、これで地獄めぐりは終了。
最後にバスに乗る前に
名物の「大オニバス」の前で写真を撮ってもらいました。

バスターミナルでバスを降り、歩いてホテルに向かいます。

別府タワー?

駅に近い亀の井ホテルに2泊します。
山の方には豪華なリゾートホテルもあるのですが、
何しろ今回は「学会」なので。

だが、お風呂はむろん、温泉です。

いわゆる温泉旅館ではないので、
夕食は外に出かけました。

食べログで駅前のお店を予約。

居酒屋チェーン店でしたが、
これが、なかなか侮れない。
サスガ、海あり県は違う。

これ、鶏ではなく、マグロ尾の身のから揚げです。

ビールもススム。

こちらは、抹茶アイスなんか頼んでいました。

あー、マンゾク。
アジもサバもいっぱい食べました。
明日から学会かー。
気分的にはいま一つ気合が入らないけど。

まあ、こればっかりは仕方がない。

続きます。


2023.11.09
11月8日早朝、5時9分の東武線の始発に乗るために家を出る。

空は晴れている。
月と金星。

今年になってこの始発を利用する回数が激増した。

平日なので、出勤のサラリーマンと思しき人がちらほらいるが
毎日こんな早い時間に通勤してるのであろうか。

舘林から特急リバティに乗り換え。

久喜駅6時発の上野東京ラインへ。
この列車は残念ながら上野どまりなので、
上野駅で乗り換え。

そして、東京駅に7時2分に着くと、7時12分発ののぞみ9号。
前回津市の鼻科学会に行った時にはのぞみ11号であったが、
今回は、ちょっとあわただしいが、
どうしてもこの9号に乗らなくてはならなかった。
そのわけは後ほど。
チケットレスのスマートEXになって乗り換えがスムーズになった。

無事に乗り込むことが出来ました。

前回が深川めしだったので、
今朝は、これにしようと決めていた。
前回も、サーモス、ペットのお茶を用意したが
新幹線の車内販売が終了するのは10月いっぱいであった。
で、今回はないのかと思っていたが、実はグリーン車だけは
アプリから注文できるのであった。
隣のサラリーマンがコーヒーを頼んでいた。

まあ、これでまた旅の経験値が上がった。
このお弁当も美味しいなあ。

妻は、おにぎり弁当。

右側の席を選んだので、晴れている今日は富士山が見える。

きれいなのでアップで富士山を撮ろうと思ったが、
車窓から富士山を取るのはなかなか難しい。

いらない看板が入ってしまったり、

木立に遮られたり、

上りののぞみ号を撮ってしまったり、

やっと撮れた。
雲がいい感じです。

今回は小倉まで4時間45分も新幹線に乗ります。
長い時間列車に乗るのはムカシから非常に好きです。
しかもグリーン車。
若いころはグリーン車など一度も乗ったことはなかったですが、
歳をとって、こんな贅沢ができるようになりシアワセです。
コーヒーを飲みながらゆっくり本が読める至福の時間です。

とか言ううちに、もう山口。

お、なんか、呼び捨てで呼ばれた感じ。
次、オレの番すか。

小倉駅で新幹線を降り、
在来線の特急ソニックで別府に向かうのだが、
実は、この小倉駅の乗り換えが、
今回の旅行中の最も重要なミッションを含んでいた。
一つは乗り換えの間に昼食用にある駅弁を買うこと。
そして、もう一つは特急ソニックの乗車券、特急券を
みどりの窓口で受け取ること。
新幹線はスマートEXでチケットレスなのだが、
JR九州はアプリから乗車券の予約、決済はできるが、
その予約番号とクレジットカードをもって、
実際に駅で紙チケットを発券してもらわなければならない。
しかも、新幹線から在来線への乗り換え時間は16分しかない。
なので、あらかじめインターネットで小倉駅構内の地図と、
弁当売り場、みどりの窓口を確認しておき、
通るべき導線を頭に叩き込んでおいた。
まず3階新幹線ホームから、2階に降り、新幹線構内の駅弁売り場に直行。
ここで、狙いの駅弁を無事ゲットし、
新幹線改札を出て、みどりの窓口へ。
ここまでは大変順調であった。
しかし、みどりの窓口、けっこう人が並んでいる。
開いてる窓口は2つしかなく、
そのうち1つは、2人組のおばちゃんが駅員とあーでもない、こーでもないと
交渉してるので全く進まず、
実質、稼働している窓口はひとつだけであった。
発車時刻は迫ってくる。
ピンチである。
ワレワレの2個前にいたサラリーマンの順番になった。
このヒトさっきからスマホ開いて、カードも持ってるから、
きっとワレワレと同じく予約した特急券の発券だな、
と踏んでいた。
すると、その人と窓口の女性との会話で、
「ここはJR西日本の窓口なので、
そのチケットは、こちらで無くて、JR九州の窓口のほうです。」
という言葉が、耳に入ってきた。
あわてて、窓口を離れ外に出るサラリーマン。
きっと、そうだ。
ワレワレのチケットもここではない。
確認をとってるヒマはないので、
瞬間的にそう判断し、列を離れ外に出た。
JR九州の窓口がどこにあるかは聞き取れなかったが、
あの男を追えば、きっと行くはずだ。
トランクをもって、その男を追う。
なんか、スパイ映画みたいになってきた。
階段を上って、左側に曲がったところにみどりの窓口があった。
男性に続いてワレワレも入り、
男性が向かった自動券売機の隣に滑り込む。
チケット受け取りのボタンを押し、
予約番号と携帯番号を入力して、クレジットカードを入れると、
なんとか無事、乗車券、特急券が発券できた。

かくて、発車時刻のギリギリにホームにたどり着くことが出来た。
国鉄が民営化されJR各社に分かれたが、
システムが連携していないのは大変不便である。

12時09分発の特急ソニック19号大分行き。
グリーン車は先頭車両であった。

ゆふいんの森号もそうだが、JR九州の特急列車はどれも洒落ている。

この列車に乗って、このお弁当を食べるために
東京発7時12分ののぞみ9号に乗る必要があったのだ。
折尾駅のかしわめし。
なんと大正10年から発売されているというから
今年で102年目という超ロングセラーである。
いただくのは今回、3回目。
以前食べた時はちょっとアレな時だったが。

これこれ。

いやー、旅気分がたかまるわ。

しかも、ソニックの最前列は運転席から前方が見えます。

これもまた「乗り鉄ゴコロ」をくすぐります。

途中通った中津市は福沢諭吉の出身地だとか。
駅前にでっかい1万円札がある感じ。

かくして、別府到着。

インターネット列車予約はカンタンだが、発券は面倒でした。(-_-;)

長くなったので、この後は「後編」へ。


2023.11.06
秋は学会シーズンです。
学会に参加する第一の目的はもちろん
日々新しくなる医学、耳鼻咽喉科学の知識を
常に最新のものにアップデートするため。
大学病院や、医局にいたころは、
そうした医学の最新情報はほっておいても入ってきたのですが、
開業すると、そういった学会で得られる新しい知識がないと
とてもやっていけません。
講演を聴いていると、
普段診ている患者さんの中に
思い当たる症例を発見することがあります。
ああ、あの人はこれだったのか、と。
そして、学会で学んだ新しい知見を試してみると、
今までなかなか改善しなかった患者さんが良くなる、
ということをしばしば経験しています。
学会に行くとなると
休診にしなければならないので収入が減る、
と考えてる医者はいるみたいだが・・・・。
2つ目は、むろん、専門医更新のための単位を取得するためですが、
これは、おそらく年2回+αくらいの参加で何とかなるはず。
専門医所得していない耳鼻咽喉科医院のセンセイは
これも関係ないのだが。
そして3つ目は、学会にかこつけて、
現地の美味しいものをいただいたり、
旅行を楽しんじゃうこと。
今年も、柳川やら伊勢神宮など行きました。
これは学会が木・金開催が多いので、
水曜日を休診にしてから、この楽しみが増えました。
去年の奈良もそうだった。
なんで、今回は開催地で選んでしまった。
別府なら、会場近くのホテルでも温泉だし。

もちろん、小児耳鼻咽喉科は開業医にとって大変重要な分野で、
ためになりそうな講演も多いので、
木・金は当然学会に出ますが、
開催日前日の水曜日午後は別府地獄めぐりに行く予定。
ここはもともと休診日なので
ご容赦いただきたく。
もう、定年の年齢なので、
体の動くうちに、行けるところに行っておこう
というのが今後の方針です。
そんなわけで、11月9日(木)10日(金)は
臨時休診になりますので、
なにとぞご了承ください。
土曜日は頑張ります。


2023.09.29
続きです。
明け方トイレに起きたら朝焼けがきれいだった。

そして日の出とともに起床。
街は暗かったが、すぐそこは海だったのか。

で、今日も暑そうです。

朝食はバイキング。

ウナギまぶしご飯がありました。

へー、そうだったのか、知らなかった。
よく読むと「日本一である」ではなく、
「日本一だったことがある」というくだりがビミョーですが。

さて、今朝はシャトルバスで会場まで。

並んでるー。
20分間隔なので開始時間前の8時20分のバスは激混み。
会場までの満員バス、座れずずっと立ってました。

会場に着き、バスから降りて出勤時間帯のサラリーマンのように
一斉に会場に移動します。
ここで、日赤のS先生にお会いしました。
朝早くからご苦労様です。

今日は、領域講習のシンポジウムを午前中いっぱい聴いて、
会場を後に帰路に着きます。
シャトルバスに乗ろうと思ったら、
昼間の時間はサービスなし。
妻がタクシーアプリ持ってたからいいようなものの
無かったらヤバかった。
ホテルで荷物を受け取り、近鉄特急で名古屋まで。

名古屋駅で駅弁を買って新幹線に乗ります。

味噌カツ弁当。

そんなに好きではないが、これも旅情を重視。

このお弁当、半熟卵がついているが、
最初はそのまま食べて、

途中で、卵を絡めてお食べください、というもの。
名古屋人はこの「ひつまぶし方式」が好きだなあ。

足利市に近づくころ、日没です。
今日の日の出から日没までフルに活動しました。

明日土曜日は、外来、混むだろうなあ。


2023.09.28
続きです。
さて、今日の天気は良さそう、というかまた猛暑のようだ。

やっぱり。

朝7時に朝食をとり、支度をしてホテルをチェックアウト。
ホテルのエレベーターはボタンに指をかざすだけで
スイッチが入るタイプであったが、
やはりコロナ以降導入されたのであろうか。
エレベーターのボタンから感染した人は世界中にいるだろうか。

ホテルを出るとすぐそこが駅。

三重県に来ることはあっても、お伊勢参りはもうないだろうなあ。

などと思いつつ顔出し看板に入ってみる。

こんな、地味キャラもいたのか。

そうでした。
Suicaは使えない。

だが、今回は並走する近鉄特急で行きます。

これの方が早い。

驚いたのは、この特急券、検札しなくても
磁気の力で座席情報のランプが点灯する仕掛けのようだ。


湘南新宿ラインなどのグリーン車みたいに
Suicaを座席上のセンサーにわざわざタッチする必要はなく
ポケットに入れとけば勝手に点くらしい。
やっぱ、私鉄の方が優れている。

さて津駅に着。
こんなところに「江戸橋」駅があるとは。

駅東口すぐの今夜泊まるホテルに荷物を預けます。
西口の学会シャトルバス乗り場に行ったら、すでに出たあとのようだったので
タクシーで学会場まで。

会場は三重総合文化センター。

受付を済ませ、開会式の前に会場入り出来ました。
まだ、人がいない。

午前中いっぱいシンポジウムを聴いて、
ランチョンセミナー会場へ。

お弁当はなかなか美味しそう。
周囲に食べるところもなさそうだし。
何より外は暑すぎ。
今日は1日会場で過ごします。

今回機器展示は廊下でやってます。
廊下はあまり冷房がないので業者さんはかわいそう。

午後も領域講習まで全部聴講。
終わったのは午後6時15分。
よく、頑張りました。
シャトルバスに乗ろうとしたら、この観光バスは某ホテル行きで
津駅行きは別。

こっちは路線バスでした。
三重交通のバスに乗ると去年の鈴鹿を思い出すなあ。
このバスも先週末は大忙しだったことだろう。

さて今回の宿泊はこの津駅に隣接したビジネスホテル。
夕食は駅近くの居酒屋に行ってみます。

YEBISU公認店、の看板につられて入ったこの店。

あとから知ったが実は九州料理の店でした。

まあ、いいでしょう。

ワタシとしてはエビスビールがあればえびす顔。

しかも大ジョッキがある。

しかも時間限定で大ジョッキが中ジョッキ価格で飲める。
これは注文するしかねー。

今日聴いた学会の講演についてあれこれ話をしながら、
にぎやかな晩餐。




ウマかったー。

さあ、明日もまたがんばるぞ。
それにしても明かりの少ない県庁所在地。

続く