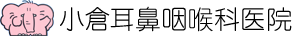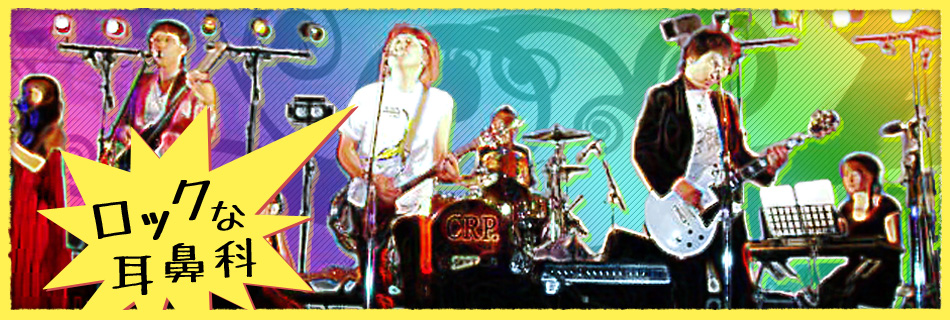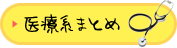2009.11.06
あー、今日の午後は疲れたぞ。
インフルエンザは依然として猛威をふるってるし、
風邪引き、ハナタレから中耳炎になる子も増えて来た。
しかも、金曜の夕方は滲出性中耳炎の子の手術が多い。
鼓膜切開をした場合、耳だれなんかが出ちゃうことがあるので、
翌日診察をすることにしてる。
すると、親の仕事の関係で平日なかなか来院できない子は、
金曜日の夕方切開して土曜日に再診、なんてパターンが多いのだ。
特に今日は鼓膜切開が1歳と2歳の2名3耳あったが、
あらかじめ予定手術として4歳児の鼓膜チューブ留置が入ってた。
Sちゃんは4歳の女の子だが滲出性中耳炎がずーっと治らない。
これまでに鼓膜切開を両耳3回づつしたけど、
いずれも粘っこい滲出液が満タン。
そして、その穴が開いてるうちは良いが閉じるとともに水がたまっちゃうのだ。
それで、チューブ留置を勧め、2週間前に右側を手術。
左は先週の金、土でやるはずだったが、
先週私のほうでお通夜に行く用事が入っちゃったので今日になった。
問題はSちゃん、あばれ方が半端じゃない。
診察で耳を見るだけでも大暴れ、お父さんはいつも汗だくだ。
普段はおとなしいが診察台に座ると突然豹変する。
エクソシストとかあんな感じだ。
2週間前の手術もそれはそれは大変だった。
それでいて、家では妹(今日の鼓膜切開の2歳児)と一緒に
「ジビカごっこ」をしてるらしい。
「ハイ、お耳、みてみますね。」なんて。
実はこの妹も大暴れムスメなのだ。
今日もSちゃん、鼓膜麻酔まではおとなしくさせるのだが、
いざ診察台に来ると大暴れ。
麻酔をすると耳の痛みは全くないのだが、
恐怖心で激しく全身を使って抵抗する。
スタッフ4~5人で抑えるが一瞬たりともじっとしていない。
ものすごい力だ。
ちなみに家での「ジビカごっこ」では、あばれるシーンは入ってないらしい。
何とか耳垢を取り、まず鼓膜切開。
視野を確保するまでが一苦労だ。
顕微鏡を動かしながらタイミングを待つ。
コンマ何秒の隙を見てメスを入れる。
果たしてドロドロの滲出液が充満。
吸引管でもなかなか吸いきれない。
やっぱ、こりゃ、チューブ必要だよねー。
さて、こっからが問題だ。
子供の細い耳の穴の奥の鼓膜に正確にチューブを入れるのはなかなか至難の業だ。
研修医では全身麻酔で20分で入れられれば上出来だが、
局所麻酔ではそんな悠長なことは言ってられない。
私は訓練の甲斐あって3秒あれば入れられるようになった。
しかし、今日のSちゃんの動きは半端じゃない。
3秒間も止まってはくれないのよ。
「オウチ、カエルー」
「ほら、もうちょっと、がんばってー。」
「ぎゃー。」
「Sちゃん、みーっつ数えようか。いーち、にー・・・」
「イーヤダー、おかね、ハラウー。」
ちなみに「お金払う」とは、いつも診察後お会計すると帰れるので、ということらしい。
金でこの一件を示談に持ち込む、という意味ではないようだ。
みんなで押さえること2~30分。
私は顕微鏡を動かしながら、ずっと鉗子をもって、チャンスを待ってる。
そして、一瞬止まった隙を見てチューブを挿入。
その間1秒足らず。
「よし、入った、みたい。」
しかし、その後もチューブがちゃんと入ってるか確認するのに
大暴れが止まらず、またしばしみんなで格闘した。
無事入ってました。
めでたくチューブの入った鼓膜の写真を撮り、
同じファイルにSちゃんのピースサインをしてる顔写真も取り込んだ。
2週間前の写真は泣き顔だったけど、
今度チューブが入ったらピースサインするって、お母さんと約束してきたらしい。
いやー、Sちゃん、良かったねー。
これでお耳がよく聞こえるようになるぞー。
ピアノも上手になるぞ。
それにしても、粘り強くがんばったスタッフの皆さん、そしてお父さん、
大変ご苦労様でした。
きっと、明日はみんな筋肉痛だ。
Sちゃん姉妹、今夜は「ジビカごっこ」、するんだろか。
きっと、疲れて、すぐ寝ちゃうね。
おやすみなさい。


2009.11.04
季節型インフルエンザの方は毎日予防接種してますが、
新型インフルエンザの予防接種医療機関が
ようやく我が栃木県でも発表になりましたね。
関係ないけど、患者さんの中に
「季節風インフルエンザの予防接種お願いします。」
と、おっしゃる方がいた。
「きせつふう」って・・・・・、
今、秋だから注射器にキノコとモミジでも添えようかしら
などとフッと想像したりして。
さて新型の接種機関は栃木県のホームページで閲覧できますし、
おそらく明日付けの朝刊にも載るらしいです。
足利市でも当院を含め多くの医療機関が載ってます。
今後、優先接種に該当する基礎疾患を持つ方の接種がまず開始されます。
原則として、入院あるいは通院してる医療機関での接種となるので、
とりあえず当院で該当する方はほとんどいないと思いますが。
妊婦さんのほか、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、慢性腎疾患、慢性肝疾患、
神経・筋疾患、血液疾患、糖尿病、免疫抑制状態、小児の慢性疾患です。
これらの病気をお持ちでしかもその病院が新型の接種を行ってない方については、
当院でも接種可能ですが、その場合、主治医の証明書が必要です。
間違いやすいのが、慢性呼吸器疾患のうち「喘息」ですが、
「気管支喘息」で継続して治療を受けているか、治療を受けてなくても
定期的に経過観察で受診してる方などですから、
「風邪を引くと喘息っぽいね、とか喘息様気管支炎だね、といわれる。」とか、
「この子は喘息の『ケ』があるね、といわれた。」程度の方は該当しませんのでご注意を。
しかし、「免疫抑制状態」には
「プレドニゾロン換算5mg/日以上のステロイドの継続使用」
という記載があるので、
某皮膚科で
「抗ヒスタミン剤」という説明で「セレスタミン」を朝晩飲んでる人は該当しちゃうのか?
突発性難聴でステロイドを飲んでる方は持続的ではないので関係ありません。
しかし、今回のインフルエンザ騒ぎで、
毎日のように国や県からの膨大な書類に目を通さねばならない。
しかし、その書いてある文章がわかりづらいこと。
重要な点と、どうでもいいことが雑多に羅列されてるし、
文章そのものも、要領を得ないものが多い。
火災保険の約款みたいで、読む気が起きない。
ああ、大人になってからこーゆー文章に出会うから、
それで、小中高とあんなにいっぱい国語の授業があったんだな、
と感じる今日この頃。
それにしても、オメーラの方はちゃんと国語勉強したのかよ。
もっと、文章を簡潔、明瞭に書けねえのか、とも思ってしまう。


2009.10.27
今週から当院でも従来型のいわゆる「季節性インフルエンザ」の予防接種を開始しました。
まだ、余裕がありますが、ご希望の方は早めにご予約ください。
どうせ、今年は浦和レッズの「優勝記念インフルエンザ半額セール」はありませんので、
待っていても無駄ですぜ。
いっその事、
「浦和レッズ不振下位低迷、天皇杯&ナビスコ杯敗退記念インフルエンザ倍額セール」
をやりたいくらいじゃ。
あっ、イカン、この辺の話題になると、
つい気持ちが、ささくれているもんで・・・・。
冷静に・・・・。
一方、並行して「新型インフルエンザ」も、毎日出てますね。
インフルエンザの予防接種をしながら、
一方でインフルエンザの検査、治療をすることは
今までなかったことで、ちょっと変な感じですね。
先日ブログに書いた困った開業医の先生の噂が伝わったのか、
今日、医師会から
「タミフル、リレンザの予防投与はダメよ」
という内容の連絡の書類が来た。
あの小児科の先生、ちゃんと読んだかしら。
そして、新型のワクチンの方も、先週末に届きました。
しかし、各医療機関からの申請が多かったようで
当院の割り当ては3人分のみでした。
で、私はというと、以前書いたように注射キライなので、
自分の分は、知り合いの娘さんで障害のある17歳の女の子に回しちゃいました。
これ、当局が知ったら私は罰せられるのかしら。
でも、いまだ口も利けない身の回りのこともできない彼女がインフルエンザになったら、
そっちのほうが絶対ヤバイ、でしょ。
だから、ブログを読んだ人はこのこと告げ口しないように。
(じゃあ、わざわざ書くな、って話もあるが、
実はホントのとこズイブン書くの迷ったんですが、
この間ブログにあんなこと書いたので
で、どーだったのよ、と思ってらっしゃる方も少なからずいらっしゃるか、と思いまして。
しかし、これで「新型」にかかって死んじゃったら、そーとーカッコ悪いなー、オレ。)


2009.10.22
【その1】
昨日来た、患者さん(女性、成人)の話。
37度台の熱があり体がだるい、とのこと。
「周りにインフルエンザの方はいましたか?」
「高校生の息子が先週39度までの熱が2日続いたんですが、
近くのお医者さんでインフルエンザではないといわれました。」
「学校ではどうなんですか。」
「それが、息子のいる2年生はそうでもないんですけど、1年3年は大分多いという噂が・・・。」
「噂?」
「学校側が公表しないんです。」
話としては、その高校(足利市内ではない)では、1年生、3年生に
インフルエンザと思われる多数の欠席者があるのに、
保護者には特に連絡をせず、修学旅行なんかも行っちゃったらしい。
最近、世の中でインフルエンザが流行ってるので注意しましょう、
というプリントが来ただけだという。
これ、ダメですね。
風評被害を防ぐため隠蔽した、としたら問題ですね。
こういう、社会に影響を与える情報は、なるべく早く、広く、正しく伝えるべきです。
自然災害でも、事故でも、伝染病でも「正確な情報」が、最も重要です。
【その2】
そして、今日の午後来たアレルギー性鼻炎の小学5年生の男の子。
「また、鼻炎出てきたね、お薬出します。」
すると、お母さんが
「この子、お姉ちゃんがインフルエンザだったので、予防してるんですが。」
「予防?」
「ええ、リレンザを。」
「リレンザ!この子なんか病気あったっけ、腎臓とか糖尿とか・・・。」
「何もないです。」
「何か症状あるの?」
「咳ひとつしません。」
「だー、どこの病院?」
「×××です。」
「また、あそこか。ひょっとして、お姉ちゃんは他に薬何か出てる?」
「トミロン出てます。中耳炎とかにならないようにって。」
あー、全く話にならん。
新型インフルエンザで耐性ウイルスが出てるから、
タミフル、リレンザの予防投与は控えるようにと、
WHO(世界保健機構)が通達を出したのは9月のこと。
それを受けて、厚労省も同様の勧告を行っている。
「予防投与のリスク」「アメリカCDC」参照。
その前、7月に大阪で見つかった新型インフルエンザの耐性ウイルスも、
予防投与を受けていた40代の女性教諭だった。
そもそも、季節性のインフルエンザでも予防投与は、
ごく限られたハイリスクの場合しか認められてないし、それも保険適応はなく自費扱いだ。
なんか、こんな話聞いて、情けなくなってガックリきて、
そのあと、夕方、仕事するのがしんどかった。


2009.10.20
さて、新型インフルエンザワクチンについては、
お上から全く音沙汰がありませんが、
患者さんは、毎日出てますね。
実は、新型インフルエンザのワクチンの優先接種順位が発表されてから、
ずっと、悩んでることがあります。
それは、オレ、ワクチンどうしよう、ということ。
世の中には、インフルエンザになると重症化して死んじゃうかもしれないリスクを持った人がいる。
そんな人を差し置いて、オレが打っていいものかと。
ワクチンがみんなにいきわたればいいけど、ずっと「足らない」といわれている。
じゃあ、オレの分ももっと必要な人のとこに回したい、と思うわけだ。
オレがかかっても多分、死ぬことは無いだろう。
2~3日仕事休むかどうかだと思う。
もちろん「感染源」になってしまうとマズイ、という考えはあるが、
別に入院患者さんがいるわけじゃなし、自分に「感染力」があるかどうかくらい、
医者であるから、わかるはずだ。
ただ、たった一人分をどこにまわすかっていうと、これがナカナカ難しいんですけど。
何かいい考えはありませんか。
以前、患者さんにいわれたことがある。
「お医者さんが風邪引かないのは、
何か一般人には手に入らない、いい薬とか注射とかがあるんですか。」
これは、驚きましたね。
もちろんそんなものないし、あればまず患者さんに使うって。
以前、タミフルがなくなっちゃった年、
自分用にとっておいたタミフルを患者さんにゆずっちゃったこともあったなー。
(「タミフルの消えた冬」参照。)
日々、さまざまな菌やウイルスを浴びてると、次第に「免疫」がついてきて
ワクチン打ったと同じ状態になることはあります。
「新型」もそろそろついてたりして・・・。
と、思うと、ますます打つのが申し訳ない。
あと、もう一つ。
・・・・オレ、注射キライだし。


2009.10.19
今日から、医療従事者は新型インフルエンザのワクチン接種が開始されます。
って、朝のニュースで言おうが、どこにもワクチンないよ。
何の連絡もないよ。
というわけで、今日もたくさんの新型インフルエンザの患者さんの診察をする。
ワクチンまだ打ってないのに、自分は相変わらずマスクもしてないけど。
(職員にはみんなしてもらってますが)
その代わり手洗いは、ヒマがあれば、いやヒマが無くてもやっていて、
外来のペーパータオルはどんどん消費されていく。
言っとくけど、インフルエンザ、なんといってもうがいより手洗いです。
うがいはたいして効果が無い、と考えていいが流水の手洗いは効果的。
ただし、タオルは使い捨てのペーパータオルですよ。
それにしてもインフルエンザ、急激に増えてますね。
市内のある学校では、修学旅行に行ってインフルエンザが学年中に広がったらしい。
旅行中に熱で3人帰ったそうな。
いろいろ事情はあると思うが危機管理ができてませんな。
一方、季節性の従来型インフルエンザについては、当院は今日から予防接種の予約開始。
噂ではすでに予約でいっぱいでキャンセル待ちの病院もあるみたいで
受付は朝から電話応対に追われてた。
ところで、最近思うのですが、季節性のインフルエンザ、今年はどうなるんだろうか?
かつて、「スペイン風邪」といわれたインフルエンザはH1N1であることが後にわかった。
その後、1957年「アジア風邪」と呼ばれるH2N2型が流行した時にH1N1は姿を消した。
さらにその後「香港風邪」と呼ばれるH3N2型が流行し、その前のH2N2は姿を消したのです。
それが1968年のことです。
つまりココまでは、A型は流行するのは常に1種類、ってことになります。
しかし、1977年に流行したソ連風邪はH1N1型。
つまり消えていたスペイン風邪の亜型だったのです。
そしてこの時に、H3N2は消えなかった。
だから、最近はAソ連型、A香港型、そしてB型が毎冬流行し、
予防接種もその3種類が入ってます。
新型インフルエンザはH1N1の亜型です。
さて、この冬、果たしてソ連風邪は姿を見せるのか、
新型の登場とともにまた消滅するのか?
はたまたA香港型はどうか。
ひょっとして、従来型、出なかったりして・・・。
まあ、それはわかんないし、B型は少なくとも残るだろうから、
とりあえず従来型ワクチンは打っといたほうがいいですけどね。


2009.10.16
インフルエンザはここに来て急激に増えており、
当院でも毎日数人が診断されてる。
患者さんが意外と冷静なので大変助かってます。
また、学校にしても、今回はきちんと早めに「学級閉鎖」をしてくれるので
流行の拡大がある程度緩和されてるようだ。
今までは冬にインフルエンザが流行ると、
「始業時間を1時間遅らせる」
というわけのわかんない処置が施されていた。
一体、あれは誰が考え出したんでしょうね。
何の効果もないばかりか、
1時間遅れなら、なんとか無理して学校行っちゃおうか、なんていう子供も出るので
かえって、流行は拡大し、長引く恐れがある。
今回は始業を遅らせるか、という議論は出なかったのか、
そこら辺の校長先生に訊いてみたいもんだ。
今ぐらいで、推移してくれれば、タミフル、リレンザも安定供給され、
適切な治療が受けられるはず。
まだまだこれからでしょうが、季節性のインフルエンザや一般の風邪が流行る前に
ある程度沈静化してくれるといいですね。
大事なことは、正しい知識と落ち着いた対応だと思います。
そのためにはきちっとした情報の開示が肝心でしょう。
その割りに、国や県からの情報は、我々医療機関にきちんと渡ってるとはいい難い。
新型インフルエンザのワクチンについて、来週から接種が始まるわけですが
この情報がほとんど入ってこない。
マスコミにはいろいろリークされてるので患者さんからの問い合わせも多いのだが
お上から何も言ってこないので、
こちらとしては「ワカリマセン」としかいえない。
先週の土曜日、毎日たくさん来る郵便物の中にある封筒を発見。
栃木県医師会からで「重要」のスタンプが。
これが、なんと各医療機関に新型インフルエンザ接種医療機関を募るアンケートの書類だった。
見れば13日までに返信のこと、とある。
文書の日付が10月8日。
普通郵便だからおそらく9日午後に配達されたんだろうが
私が発見したのが10日土曜日。
だって、11日、12日は連休だぞ。
一応その日に郵便局に直接持ってったけど、なんか連絡いい加減。
連休明けの13日に病院に行って、初めて封筒を開き、あれれという先生だっているだろうに。
そもそも、こんな重要な書類は普通郵便じゃなく、配達確認とか、医師会から手渡しとか
もっと確実な方法で、渡すべきでは?
で、今日までの時点で問屋さんにワクチンが入荷したとの知らせも、
こっちが出したアンケートの返信に対する、お役所からの返事もない。
ホントにお役所、大丈夫?


2009.10.01
先日の専門医試験について関係者(?)の方からコメントを頂いて、
そんなに受験者の実数は多くなかったそうで、どうも失礼しました。
まあ、合格には変わりないわけだし、
日々の禁煙指導にも力を入れる今日この頃なんですが、
今日来た患者さんの話。
若い女性なんですが、勤め先の美容院(?)で、酸素タンクに入ると鼻が痛い、とのこと。
酸素タンクって、高圧酸素療法のことですか、
そんなのが美容院にあるんかい?
と、訊ねたら、今ではあちこちにある、って話。
うちの職員も知ってた。
何のために入るの、って訊くと
「美肌効果」「気持ちがすっきりする」
へー。
スタッフなので1時間1000円で入れるんですよ。
えー、そんなに金取るの。
ときいたら、1000円は破格に安いらしい。
5000円以上とるとこはざらだとか。
うーむ。
高圧酸素タンクはそもそも医療機器で、ホンモノは高価なため
大学病院レベルでしかない。
一酸化炭素中毒やバージャー病、ガス壊疽、潜水病などで使用されるが、
耳鼻科領域では突発性難聴への効果があるため我々には馴染み深いものだ。
要するに「ヘンリーの法則」ってのがあって(高校で習いましたね)
気体の圧量を高めると溶解度が増す、という。
だから血液中に余計酸素を溶け込ますことができるわけだ。
理論的には循環が改善し、体が元気になる可能性もあるけど、
さて、実際の効果はどうなんだろ。
美肌効果は、疑問だし、ダイエットに関してはもう全く関係ないでしょう。
疲労回復も気分的なものが多いでしょうね。
まあ、以前書いた「点滴パーラー」ほどはあくどくないが、何となくコンセプトが似てる感じ。
少なくとも1時間で何千円も払う価値はないでしょうね。
1000円だって高い。
800円で日帰り温泉入ったほうがずっといい。
実際、私も大学病院勤務の頃、頚部膿瘍の患者さんをストレッチャーに乗せて、
何回か入ったことがある。
特に疲労回復した覚えはないが・・・。
アレルギー性鼻炎、花粉症や、中耳炎の既往がある人などは、
中耳炎の発症や、鼓膜に穴が開いちゃったりすることもあるので要注意ですよ。
ちなみに今日の方の場合アレルギー性鼻炎があるので
中鼻道の閉塞からの、いわゆるリバースブロックが原因と思われます。
ただ、少なくともこの方の場合、
1日20本弱吸ってるタバコをやめることのほうが
酸素タンクに毎日入るよりも、美肌や疲労回復には数千倍の効果があるのは
まず、間違いないでしょう。
逆にお金もうくしね。
みんな、よく考えてね。


2009.09.30
先日来院した女子高生。
「今日はどうしましたか?」
と訊ねると
「くさいだまが気になります。」
との返答。
「!?クサイダマ????」
初めて聞いた単語だ。
「それって何なの?」
「くさい玉が出るんで、友達に訊いたら、それくさいだまだから耳鼻科で取ってもらえば。」
と、言われたそうな。
「!」
ははあ、あれかな。
「それって、たまに口から出る1~2ミリのカスみたいやつで、
ぐずぐずしてて、白っぽい黄色でくさいニオイがするやつ?」
「あ、それです。」
なるほど「くさいだま」って言われてんのか。
誰がつけたか知らんがなるほどねー。
念のためパソコンで調べると、ホントに「くさいだま」でヒットしてくる。
正確には「膿栓」といいます。
口蓋扁桃(俗に言う扁桃腺)にはぽつぽつ穴が開いています。
この穴が大きい人はそこに食べ物のカスや雑菌が繁殖して
カッテージチーズのカケラみたいな塊りができます。
自然に取れたときある程度の大きさがあると、
口の中に異物感を感じ、吐き出してみるとくさいのです。
ほとんど病的なものはありませんが、
中には繰り返し大きなものがたまったり、口臭の原因になることもあります。
外来で簡単に取れちゃうのですが、扁桃のポケットの大きい人は
また、たまっちゃう事は多いです。
重症例は扁桃腺そのものを手術で取ったりするわけですが、
通常は、うがいや口腔ケアだけで経過を見ます。
溶連菌感染以外は抗生物質も不要です。
しかし、「くさいだま」とはよく名づけたもんだ。
なんか、ポケモンの名前かと思った。
勉強になりました。


2009.09.29
先日、札幌まで行って受験してきた「日本禁煙学会認定指導医試験」に
私と妻とそろってめでたく無事合格しました。
ああー、よかったー。
休診にして行った以上、「結果を出さねば」というプレッシャーがあり、
また、副院長だけ受かって私が落ちてたらカッコ悪いなーなんてのもあったりして。
試験前は、なんとなく受かるんじゃないの、なんていう楽観論に支配されてましたが、
いざ、会場に行くと、受験生モード全開の先生方にびっくり。
しかも200人を越える受験者。
試験会場も、試験開始ぎりぎりまでみんなテキストを放さず、
ウチはテキスト2人で1冊というセコイ体制なので、
待ち時間手持ちぶたさで落ち着かなかった。
試験は結構できたと思ってはいたが、
法令関係の問題が意外と多く、苦戦したので、心配はありました。
でも、落ちたから、医者ができないわけじゃなし、
次の試験は来年9月、会場が四国は愛媛松山だって言うんで、
落ちたら、今度は道後温泉、ポンジュースじゃー、と思ったのですが。
そもそもこの試験を受けるきっかけは当院が禁煙外来を始めたことに端を発します。
禁煙外来は検査機械をそろえ施設基準を認可してもらい、保険診療ができるのですが、
我々は医学部でも研修医時代も「禁煙学」というものを系統的に学んだことがありません。
禁煙外来に資格は要らないけど
お金もらってやる以上、やはりきちんと勉強したいと思いました。
そして、この試験のことを知り、やっぱ取っといた方がいいだろう、
っていう事で受験に至ったのです。
今朝、学会からメールが来てて、
試験結果が発表になりました、とのこと。
しかし、そこには結果は書いてない。
合格者66名はホームページから閲覧できます、って、
合格者66人しかいないのかよ。
ざっと200人以上は受けてたのに。
(ちなみに私の受験番号は152番、副院長は150番。)
こっそりホームページを開き、2人の名前を確認しました。
合格率なんと3割強、よく受かったもんだ。
「最初からこんな合格率だって知ってれば、もっと勉強してたよねー。」
なんて、妻はのんきなこと言ってますが。
思い返せば受験当日、試験前のセミナーからも出題される、
ってことで一生懸命ノートとリながら聴いたわけです。
その講義の始まる前に、何やら小さい金属の箱を机に並べる妻。
「なに、それ。」
「これ、ミントのキャンディー。あたし、この手の講義すぐ眠くなっちゃうから。
こっちがスースーするやつで、こっちがもっとスースーするやつ。
舐める?」
「いや、いい。」
で、講義が始まって少しして横にいる妻に小声で話しかける。
「ねーねー、今の患者さんの話さー、・・・・ん?あれ。」
もう寝てるじゃん。
あわてて袖を引っ張る。
「(小声で)こら、起きろ。飴舐めろ。」
ま、その後はずっと起きてたみたいですが。
そんなこんなで無事合格してよかったです。
別にこれで、収入が増えるとかじゃないんですけどね。
日本禁煙学会の「禁煙キャンペーンコマーシャルコンテスト」の入選作品の動画を
当院のホームページに掲載しました。
「小倉耳鼻咽喉科」のホームページを開いていただき横の「禁煙外来」の
ボタンをクリックしていただけると見られます。
なかなか傑作ぞろいですので是非一度ご覧ください。