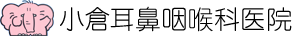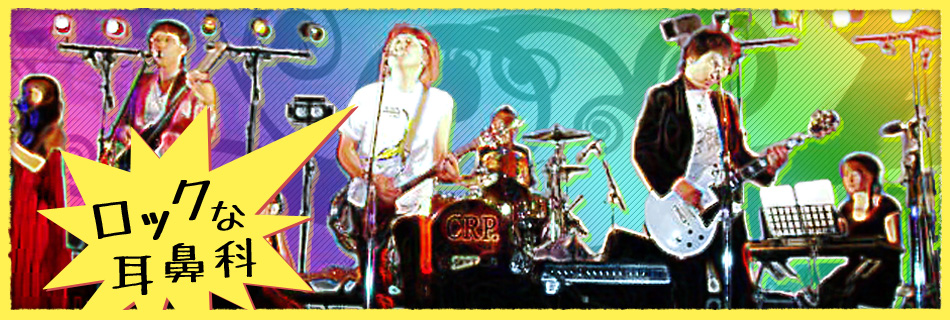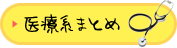ブログトップに戻る
2021.01.09
1都3県に緊急事態宣言が発出された1月8日の前あたりから、
また、外来の患者さんの数がぐっと減りました。
もともと毎年、年末までは患者さんが多いが、
年末年始のお休みがあると、
耳鼻科の患者さんの大半を占める
子供の風邪ひきがいったん収まるので、
年明けは患者さんが減る時期ではあります。
このあとは、いつもですと
インフルエンザの患者さんが増加するのですが、
今シーズンは全国的にも流行は無く、
今後も国民全体で感染予防を続ける限り、
流行はおそらくないだろうと考えられますので、
これに関しては患者さんは開院以来初の
インフルエンザ患者数ゼロ、ということになるかも。
1月は花粉症のレーザー治療も多いのですが、
今年は予約がスカスカで、
皆さん、コロナ騒ぎで、
花粉症のことは忘れてるな、という印象です。
だが、今年は、非常に少なかった昨年に比べると、
かなり多めの花粉が飛ぶ予測も出ていますので、
くれぐれも油断なきよう。
今週になり、目がかゆい、鼻がムズムズ、などの
花粉症様の症状で受診される方が目につきました。
まだ、本格飛散は1カ月半くらい先なので、
ハンノキの花粉なのかもしれませんが、
毎年スギ花粉症があり、
今年すでに症状のあるかたにはクスリを2~3か月分出して、
今のところは症状に応じて、
2月後半からは連続的に飲んでくださいと指導しています。
以前から当院に受診されてる方には、
毎年、シーズン初めに来ていただき、
以前の検査結果に応じてそのシーズン分のクスリを
目薬、点鼻を含めて2,3か月分まとめて出すことにしています。
そうすることで、患者さんの来院日数を、
年1回程度にすることができ、
待合室の混雑を緩和することが狙いでしたが、
今年は、新型コロナウイルスの対策にもなりますな。
外出を控える分、花粉の曝露は減る、という見方もありますが、
暖かくなってくると、密になる屋内を避け、
公園や、動物園などの野外での活動が増えれば、
忘れていた花粉の攻撃を食らうことになります。
室内の換気のために窓を開けていると、
スギ花粉が室内に循環して、
花粉が「密」な環境になることも考えられます。
スギ・ヒノキ花粉症の方は、
なるべく早いうちに、クスリ取りにきておいてください。


2021.01.07
外来をやってると時々医療関係者の方もかかるわけで、
そういった「ギョーカイのヒト」は、
ひょっとしたことから、アレ、と気づくことがあります。
さすがにプルスがどうの、コートがどうの
などというヒトはいませんが、
(注:プルスはドイツ語で脈拍のこと、
コートは同じくドイツ語でウンチのことです。)
「夕べ、子供が熱発しまして・・・」
などというヒトは看護師さんかもしれません。
「発熱(ハツネツ)」は一般に言いますが
「熱発(ネッパツ)」はギョーカイ用語です。
別に「銀座」のことを「ザギン」と言ったり、
「六本木」のことを「ギロッポン」というような
わけでは無いでしょうが。
「発熱」と「熱発」はほぼ同じ意味ですが、
「ネッパツ」の方が破裂音が入る分、
緊急感、切迫感があり、
熱の上がり方が急激で、高い印象です。
「37.2℃程度の発熱があります。」
とは言うが
「37.2℃の熱発です。」
とはあまり言わない。
「術後の〇〇さん、熱発してます。」
と聞くと、
おお、ヤベえ、何とかしなくちゃ、と思うわけです。
他にはベロのことを「シタ」ではなく
「ゼツ」というヒトは医療関係者でしょう。
これは医療の現場では
「舌」と「下」をとりまちがえないために、
あえて「舌」は「ゼツ」と呼びます。
同じように術後に糸を抜くことは「抜糸(バッシ)」と言いますが、
歯医者さんだけは「バツイト」というそうです。
もちろん「抜歯」との混同を避けるためです。
そういえば「血液型」のことを「血型(ケツガタ)」と呼ぶのも
医療関係者だけですが、
あれはなんでなんだろう。
たぶん「血液培養検査」のことを「血培(ケツバイ)」と言ったり、
「血液ガス分析検査」のことを「血ガス(ケツガス)」と言ったり
することからの流れなんでしょう。
子供さんのアレルギー検査で採血するときに
「一緒にケツガタも調べられますか?」
と尋ねるお母さんがいると、
お、と思ったりします。


2021.01.05
本日1月5日から2021年の仕事始め。
例年、仕事始めの日には朝からドドドっと患者さんが押し寄せて、
外来は大混雑になるのですが、
今年は様相が違いました。
トータルでは午前中だけで80人以上来院されてるので
少なくはないのですが、
来院する患者さんがインターネット予約をうまく使って、
自分の順番近くまでは来院しないで
自宅やあるいはクルマの中で待っていていただいたようで、
待合室が密になることはあまりありませんでした。
今後もこの感じで行っていただきたい。
保育園に通ってる子供たちは、
年末からハナミズやセキを反復していましたが、
この年末年始のお休みでだいぶ良くなりました。
毎年その傾向はありますが、
今年とくにその印象が強いのは、
お正月に外出や旅行、移動をした家族が少ないせいかもしれません。
まあ、また保育園は始まりますが、
緊急事態宣言が出て、自粛ムードが高まれば、
少なくとも普通の風邪に関しては
今期は過去最低レベルになるような気がします。


2020.12.29
ネットでよく見てるお医者さん専用のサイトにある掲示板に
あるスレが出ました。
耳鼻咽喉科のセンセイの投稿で、
診察中の子供の泣き声に耐えがたく発狂しそうになります、
何か対処法は?
というものがありました。
かなりオドロキです。
自称「くそ爺耳鼻科」と名乗ってるからには、
年輩の耳鼻科医で昨日今日医者になったヒトではないでしょう。
そりゃ、耳鼻咽喉科医に向いていないとしかいえません。
耳鼻咽喉科の外来では、
子供は泣いて当たり前、
だって、子供にとって病院はコワイところですからね。
診察前から泣いてる子はざらで、
中には駐車場や当院への曲がり角から泣き出す子もいるようで・・・。
でもこのスレに対するレスでは、
泣く子を怒鳴りつけるお医者さんとか、
泣く子を診るのが嫌だから内科を標榜するが小児科は診ない、
とかいうものがありました。
ワタシ自身は、子供の泣き声は、
ほぼ全く気になりません。
もう完全にBGMと言ってもいい。
いろんな泣き方をする子がいてそれもまた興味深い。
ときに殺人音波か、というほどの高周波の大騒音で泣き叫ぶ子がいて、
鼓膜がビリビリして、終わったあとも残響が残る場合がありますが、
キクー、といった感覚はあるものの
子どもが憎らしいとか、発狂しそうだとはツユほども思いません。
せいぜい、ワサビのききすぎた寿司を食べたかのようなもんです。
暴れる子もまたしかり。
処置がしにくいとか、時間がかかることで、
マイッタなー、とは思いますが、
子どもに恨みは持ちません。
チューブ入れる手術の時などは、
せめて3秒だけでも止まってほしい、
と思うのですが。
ただ、子供が泣き叫んで暴れても真剣に押さえないお母さんとか、
「痛かったねー、ごめんねー。」などと、
こちらの医療行為を否定するような保護者の方にはムッとします。
耳鼻科にかかると泣くからと、
中耳炎を小児科で治療してもらおうとする親御さんもいますが、
一定レベル以上の中耳炎は必ず失敗します。
キチンとした小児科は耳鼻咽喉科に紹介してくるのですが、
診断力のない小児科に行っちゃうと悲惨です。
親御さんが、本気で自分の子供の病気をよくしたい、
という気持ちさえあれば、
どんなに泣こうが、喚こうが、暴れようが、
こっちは一切気にしないので、
安心して受診してください。
それまで大泣きしていた子が、
頑張って泣かずに治療ができたときなどは、
こちらもうれしいのでうんとホメてあげます。
小さいころ中耳炎を反復し、
毎回大暴れしてスタッフ総がかりで抑えなければならず
診察に20分も30分もかかった女の子が、
今は中学生になって、風邪をひいたりすると、たまに受診します。
本人は照れ臭そうですが、
今また、当院を受診してくれるのは大変ありがたい。
中耳炎はキチンと治っており、
今では当時のことは笑い話ですが、
そうなったのも
暴れる子供にめげずに
根気よく通院させたお母さんのおかげだと思います。


2020.12.25
昨日の東京都の新型コロナウイルス陽性者数は
888人だそうで、
八八八と末広がりは一般には縁起がいいのだが、
こればっかりは末広がりでは
今後ますます数が増えそうなイメージがあって困ります。
当院で予約システムとして採用してるEPARKには、
口コミ投稿ができる機能がついています。
そこに12月初めにあった投稿で、
待合室が混んでるので、クルマで待ってて
スマホで呼び出すシステムを検討してほしい、
という内容がありました。
今までもネツがあるような人は
クルマでお待ちいただくようにしていましたが、
今後は、待合室が混んでるときは、
呼ばれる順番にまだ時間のある人は、
クルマでお待ちいただきスマホで呼び出すようにします。
待合室の密を避けるため、
なるべくインターネット受付をしていただき、
順番を見ながら来院していただきたく思います。
もっとも、この投稿があった12月上旬は、
患者さんの数が多く、待合は混んでいましたが、
ここ最近は患者さんの数がまたかなり減ったので、
待合室に誰もいなく、
来院者待ちになってることもけっこうあります。
それでも土曜日だけは混むので、
他の曜日に受診できる方は、
なるべく分散受診をお願いします。


2020.12.12
一時は品薄で騒ぎになったインフルエンザワクチンですが、
当院では、患者さんに、
あわてないで、との呼びかけが功を奏したか、
大きな混乱もなく、品切れにもならず、
10月以来毎日午前午後コンスタントに注射をしています。
おかげで、患者さんが殺到して
密になることもありませんでした。
今週は、ようやく週の前半にスタッフが、
そして、ワタシも土曜日に予防接種をしました。
注射はするのも好きではないが、
されるのは、大キライ。
開業してしばらくは、
自分はインフルエンザの予防接種はしていなかったが、
最近はするようになりました。
オトナは1回なのでアリガタイ。
まあ、前に言った通り、
今のところインフルエンザが流行る気配はないですが。
でも、新型コロナウイルスのワクチンができたら、
また打たなくちゃならないのか。


2020.12.02
風邪のシーズンを迎えて、新型コロナウイルスの第三波が襲来、
県内でも1日二ケタの陽性者が出るような状況になってきました。
一方インフルエンザの方は厚労省の発表で
11月16から22日までの累計が全国で46人と、
昨年同期の15,390人と比べると激減しています。
インフルエンザは不顕性感染が少なく、
症状が出ていない人からの感染力は弱いと思われるので、
このまま国民みんなが感染予防に徹すれば、
ほとんど出ないんじゃないかと思います。
その点、新型コロナウイルスは無症状の人が多く、
発症前からも感染力があるということで、
一定の対策をしていても完全には食い止められないということのようです。
生存、拡散が生物としての目標であるとすれば、
新型コロナウイルスはインフルエンザウイルスよりも
よっぽど「成功している」ウイルスであるといえますね。
ここにきてわかってきたことがいくつかあります。
ひとつは、やはり新型コロナウイルスは飛沫による
ヒトからヒトへの感染が圧倒的に多いであろうということ。
クラスターなどの発生状況を見ていると、
会話や歌などを介した飛沫、もしくはマイクロ飛沫が、
感染のメインであり、
モノを介して感染することはほとんどないんじゃないかと思います。
なので、3密を避ける、会食・呑み会を避ける、
全員でマスクをかける、ということは大いに効果があるが
ドアノブを消毒する、とか、釣銭をトレイで渡す、
などには、たいした意味はないような気がします。
たとえば、デスクに付着したウイルスを調べたら、
6時間経ってもまだ一部生存していた、などという実験結果があっても、
そのデスクのウイルスが舞い上がって気道に入ることは無いので、
皮膚からは感染しないことがわかっている以上、
手洗いさえしていれば
それほど恐れる事実ではありません。
なんなら、その机を直接舐めたら果たして感染するか、
なんていう実験結果を見てみたい。
やっぱ、空気中に浮遊するウイルスを直接吸い込むことがヤバいでしょう。
さらに吸い込むウイルス量にもかかわってきます。
ワレワレには自然免疫というものがあり、
たとえ新規の病原体でも、とりあえず処理する力があります。
ただ、一時に侵入するウイルス量が多いと、
処理が間に合わないうちにウイルスが増殖をはじめ、
感染、発症、ということになります。
なので、ウイルスを一匹も入れない、ということではなく、
一時に大量に入れない、入る量を減らす、
ということが大変重要。
むしろ、少しのウイルスを繰り返し浴びると
予防接種と同じ免疫獲得ができることもあるとも考えられます。
見えない敵との戦いですが、
経験を重ね、事象を分析することによって、
ここにきて何となく実体が見えつつあります。
相手が見えれば戦い方も見えてくるわけで、
思い出されるのはウルトラセブン第1話「姿なき挑戦者」。
この話では見えないクール星人の円盤に手をやきますが、
特殊噴霧装置で可視化できるようになると、
意外とクール星人弱かった、みたいな感じ。
アタマを使ってウイルスと戦いましょう。


2020.11.30
この間、母校の足利高校で、
職業進路講演会でお医者さんという職業の話をしました。
先日、その講演を聴いた生徒からのアンケート結果が届きました。
概ねウケは良かったようで、
どんな印象・感想を持ちましたか、という設問では
1位おもしろかった75% 2位考えさせられた 32%
3位もっと興味がわいた 28.6%・・・
具体的な感想では
ワタシが話したことの中の2点が興味を引いたようです。
ひとつは、高校の勉強で、医者になってから何が役立つか、という話。
これは、前にも書きましたが「数学」です。
参照「勉強はしておいた方がいい」
これは、当時高校生だった自分が思ってもみなかったことなので、
医者を目指す、高校生に知っておいてほしかったことでした。
高田渡の「受験生ブルース」には、
「〽サイン、コサイン、なんになる~」
というフレーズがありましたが、実は数学、役に立つんです。
ただし、天才的な「数学頭脳」は必要ありません。
逆に、医学部は「理系であって理系でない」ので
「英語」や「国語」も、当然必要。
天才的数学脳の持ち主は、理学部や工学部に行くべきです。
「生物」は一見いちばん関連がありそうですが、
細かいところは大学に入ってから学ぶので、あまり重要ではない。
っていうか、オレ受験は「物理」「科学」で「生物Ⅱ」とってねーし。
そして、もう一つのテーマは、
これも以前ブログに書きましたが、
「医者の仕事は探偵だ」ということ。
医者でもあるコナンドイルが、
シャーロックホームズのモデルにしたのは
医学部の外科教授だったというのは有名な話。
患者さんの一見関係ないように見える話や所見から、
病気の正体を解き明かすのは、まさに謎解き、
探偵の仕事です。
たとえばイネ科のアレルギーの人が、
全然関係ない季節に鼻炎を発症。
ここで耳鼻科医が必ず訊かねばならない質問は、
「ウサギ飼ってませんか?」
ウサギの餌としてよく売っている「チモシー」は
「オオアワガエリ」という牧草を干したもので、
イネ科の花粉症を起こす重要な植物です。
これは初歩の初歩ですが、
最初にこのことに気づいたときは、ヤッタ、と思ったものです。
こういう謎解きで病気の原因や診断がわかった時は
やっぱ医者は探偵だな、と思います。
さて、今回話を聞いた生徒の中から
次世代の医者が出てくるといいなあ。


2020.11.27
新型コロナウイルス感染拡大以降、
発熱患者は診ない、という医療機関も多いと聞きます。
それも無責任だが、
そうすれば患者さんは、
どこか診てくれるところに行くしかないわけで。
すると、かかりつけ医ではなく
「初診」でかかることになりますが、
患者さんを直接診察しない医療機関もあるようです。
いわゆるオンライン診療では、
高血圧や糖尿病などの慢性疾患で受診している患者さんの
投薬はできるでしょうが、
初診の発熱患者の治療はどう考えてもできない。
そして、対面診療してます、というクリニックでも
実際にはきちんと診察していないところがあるようです。
先日受診したセキの患者さんは、
某クリニックにかかってクスリを処方されました。
驚いたことに、セキ止め、去痰剤のほか
抗生物質、気管支拡張剤、解熱剤、アレルギー、
喘息用のステロイド吸入から漢方薬まで、
ありとあらゆるクスリが処方。
しかも診察は、
患者さんから2メートル以上離れたとこからの問診のみで、
聴診器はおろか、口の中を見ることもなかったそうです。
それで、どのような診断でしたか、と訊くと、
「コロナではない」といわれたそうで・・・。
根拠はコロナの人と接触してないから。
シロートか。
いくら何でもこれで医者としてカネもらってんのはヤバイ。
ちなみに、診断は
鼻の中を見たら膿性の鼻汁がのどにまわっていて
レントゲンで風邪に続発した副鼻腔炎ということでした。
山のように出されたクスリはほとんどからぶりでした。(T_T)/~~~
政府はオンライン診療を推奨してるみたいですけど、
効率ばかりではなく診療の質の確保や、
患者さんのこうむるデメリットも良く検討すべきでしょうね。
2メートルのディスタンスや駐車場での診察では
まともな医療ができるはずがない。


2020.11.18
マスク、手袋、フェイスシールド、ガウン、届きました。

この冬、各医療機関は、
①インフルエンザの診断、新型コロナウイルスの診断を行う
②インフルエンザは診るが新型コロナウイルスの診断はしない
③どっちも拒否
の3択のどれかを選び、お上に届け出なければいけない、
ということになりました。
今期インフルエンザの迅速診断を行うためには、
新型コロナウイルスに対するのと同じ装備をしなくてはならないので
当院は①を選択。

やはり耳鼻咽喉科医として、
発熱患者を一切見ない、という選択肢はあり得ないので、
ホントはやりたくないけどやらねばならない。
医者はたとえ個人営業であっても、
営利追求よりも社会的な責任を負わねばならない、
というのがワタシの考えです。
検査は院内に専用の検査室を設けられないので、
駐車場で患者さんはクルマに乗ったまま検査、
ということにしました。
新型コロナウイルスの感染拡大が連日報道されていますが、
インフルエンザが流行らないことを望みます。